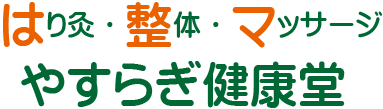抗うつ薬の副作用、本当の危険性

抗うつ薬は本当に効果があるのか?また抗うつ薬を飲み続ける危険性について具体的に説明します。
抗うつ薬の種類や特徴を具体的に知る人が少ないのはもちろんのこと、その効果、危険性について知る人も多くはありません。
抗うつ薬が開発されてきた歴史、背景、そして薬自体の構造から、うつ症状に効果があるとは断言できないことは当然ですが、体に及ぼす影響を考えると、その危険性を自分でしっかり把握する必要があります。今回は”抗うつ薬の副作用”について、具体的に解説していきます。
抗うつ薬は本当に効果があるのか?

現在、SSRIなど抗うつ薬を飲んでおられる患者さんの中で、大方の人達は「薬を飲んでいるが、さっぱり症状が良くならない」、「辛い、苦しい症状が改善しないばかりか、薬を飲むほどに症状が悪くなっているようだ」と感じておられるのではないでしょうか。
それは、皆さんが「薬は本当に効くのだろうか?」「逆に、症状を悪化させているのではないか?」という心配、不安や疑念があるからであろうと思います。そうなのです。皆さんが漠然と感じている心配、不安や疑念は正しいのです。
結論を先に申し上げます。
「薬の治療効果はほとんどの患者さんにはありません。逆に、薬の副作用によって害を及ぼすことがあるのです。」
その事実を実証する試験データが世界的に著名な医学誌に論文として発表されています。
2008年2月に米国の科学誌(Plos Medicine)に発表された論文は、4種類の抗うつ薬(SSRI)メーカーがFDA(米国食品医薬品局)へ提出した膨大な量の臨床試験データを詳しく解析して、うつ病の重症度ごと(後述します)にSSRIとプラセボ(偽薬・・抗うつ効果のない、全く無害の錠剤)との比較優位性を検討したものです。
その結果、「SSRIは効果の点ではプラセボと大差はなく、明確な治療効果は無いが、重大な副作用はある」と結論付けています。もう少し具体的には「SSRIによる効果は小さく、症状改善の80%はプラセボによるものである。うつ病が改善するのは患者本人の自己回復力によるものであり、SSRIによる薬理作用の部分は20%未満である。その弱い抗うつ効果も重症うつ病に少しは効果があるかもしれないという程度であり、軽症うつ病ではSSRIとプラセボの差はほとんど無い。」ということです。
*薬の効果が多少認められるであろうとされる「重症うつ病」の患者は、実際にはどれ程存在するのか、ということですが先の米国の研究によると「うつ病患者全体のわずか13%である」
2010年に米国医師会雑誌(JAMA)に発表された論文でも、「極度の重症患者を除けば、プラセボに対する抗うつ薬の比較優位性は乏しく、軽症~中等症の患者に対する薬効は皆無から微小である。」と結論付けています。
これらの論文などの評価により、SSRIに対する欧米の精神医学界の見方(評価)は、今やすっかり冷めたものになっています。世界中の学会が軽症うつ病に対して抗うつ薬を第一選択から外しました。
2012年に日本うつ病学会は、うつ病の大部分を占める「軽症うつ病」に対して「プラセボに対して確実に有効性を示しうる治療薬はほとんど存在しない」と発表(宣言)しています。
更には、2013年に厚生労働省が「18歳未満の若年者へのSSRI,SNRⅠの効果は認められない」と結論付けています。このような状況にも関わらず、現在の日本の精神医療の現場では軽度~中等度のうつ病患者さんに対しても、抗うつ薬が多剤、大量に、長期間にわたって処方されているのが実情です。
うつ病の重症度における分類について

英米では重症度によってうつ病の治療方針を分けているが、うつ病評価尺度などによる明確な重症度分類は設定されていません。世界的に統一されたうつ病の重症度を判定する基準のようなものはありませんが、一つの評価尺度である「ハミルトン評価尺度(HRDS)」が多く利用されています。
うつ病症状の項目を計算して総点で評価する検査尺度ですが、20点未満は軽症、20~30点は中等度、30点以上は重症度としています。一般の人が理解しやすい大まかな目安としては次のようなものです。
*軽症・・・なんとか仕事や家事ができるレベル
*中等度・・仕事や家事がむずかしいレベル
*重症度・・自宅療養が危険であり、入院が必要なレベル。重症うつ病とは、抑うつ気分が非常に重く、平常心を喪失しており、自宅で療養するのが難しいレベルのうつ病です。自殺を試みようとしたり、妄想的になったりする。
抗うつ薬の副作用による重大な影響

一般的に薬に副作用はつきものですが、抗うつ薬をはじめとする向精神薬については特別に注意を払う必要があります。それは、人間にとって最も重要でデリケートな器官である脳組織(神経細胞やホルモンなど)へ直接的に作用し、働きかける薬ですので、その副作用の内容については十分に認識し、使用に際しては最大限の注意を払うべきなのです。
更に注意すべきことは、薬の多剤併用によって生じる「薬物相互作用の危険性」です。「薬物相互作用」とは、同時に複数の薬を服用すると単独で用いた場合と比べて、薬の作用が低下したり、逆に増加したり、新たに副作用を引き起こしたりする作用です。製薬会社が医療用医薬品の添付文書に記載している副作用は、その薬を単独で服用した場合に生じる可能性があるものです。しかし、その薬が他の薬と同時に服用された場合にどの様な副作用が生じるかは製薬会社でも全く分からないのです。薬は種類が多く、薬の組み合わせは無数にあるため、どんな副作用を引き起こすのか誰にも解明できませんし、予測もつかないのです。
向精神薬の多剤、大量処方が当たり前のようになっている現在の精神医療の現場において、多数の薬の飲み合わせによって患者さんの脳の中で、どのような作用が引き起こされ、どのような影響を及ぼしているのかを考えると、その危険性の大きさを想像できると思います。
今日まで、世界的に生理学的、生物学的研究及び脳科学についての研究などが精力的に進められて来ましたが、抗うつ薬などの向精神薬が脳内でどのような作用、働きをしてどのような影響を及ぼしているのか、正確なところは全く解明されていない、というのが現実なのです。
このような状況を踏まえて、現在の精神医療の現場で危惧されることは、「向精神薬による副作用の重大な影響」と「薬物相互作用の危険性」について、薬を処方する医師がほとんど注意を向けていないのではないかと思われることです。
その認識が希薄だからこそ、安易な多剤、大量処方や漫然とした長期間の処方へ繋がって行っているのではないかと考えられるのです。
抗うつ薬の重大な副作用

(1)セロトニン症候群
(2)悪性症候群
(3)アクチベーション症候群(賦活症候群)
(4)妊産婦への悪影響
(5)錐体外路症状
(6)減薬、断薬による離脱症状(禁断症状)
(7)医療用医薬品の添付文書
(1)セロトニン症候群
セロトニン症候群は抗うつ薬の代表的な副作用の一つで、脳内のセロトニン活性が異常に亢進することにより中枢神経系や自律神経系などの症状が出て来ます。欧米に比べて日本では、この症候群の理解が遅れていましたがSSRI,SNRIが普及するにつれて認識され、注目が高まってきています。
① 症状と発症時期
主な症状は、精神症状(不安、焦燥感、錯乱、軽躁状態、意識障害など)、神経症状(振戦、ミオクローヌス、反射亢進、筋強剛など)、自律神経症状(発熱、発汗、頻脈、血圧不安定など)発症時期は原因薬物の投与開始、あるいは用量変更(追加や増量後)から24時間以内に発症することが多いとされています。
② 原因薬物
セロトニン作動薬が原因薬物で、単剤より2種類以上の併用で発症することが多いとされています。代表的な薬物はSSRI,SNRI,三環系抗うつ薬、MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)などです。
*SSRI,SNRI
近年、SSRIは使用が増加し三環系抗うつ薬、炭酸リチウム、抗パーキンソン病薬などとの併用例で発症の報告が多くなっています。
*三環系抗うつ薬
クロミプラミン(アナフラニール)はSSRIに匹敵するセロトニン再取り込み阻害作用を有しており、イミプラミン(トフラニール)やアミトリプチリン(トリプタノール)もセロトニン再取り込み阻害作用が強い薬です。
*MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)
MAOIはセロトニンの分解を阻害することによりセロトニン活性を亢進させます。このため、SSRI,SNRI,三環系抗うつ薬とは併用禁忌です。MAOIはその副作用と併用できない薬の多さなど処方上の制約が多いことから、日本では現在、ほとんど使用されなくなっています。
*その他
セロトニン再取り込み阻害作用とセロトニン受容体遮断作用を併せ持つトラゾドンやセロトニン受容体作動薬のタンドスピロンも報告されています。また、セロトニン作動薬にリスペリドンなどの抗精神病薬を追加した後に発症したという報告もあります。
③ 治療
本症候群が疑われるときは、直ちに医師の適切な処置を受ける必要があります。
まずは原因薬物を中止して、全身管理と補液を行います。セロトニン症候群の予後は良好なことが多く、大部分は24時間以内に改善しますが、場合によっては高熱症、けいれん発作、昏睡、血圧低下、心室性頻脈、代謝性アシドーシスなどを合併すると重篤な経過をたどるケースもありますので十分な注意が必要です。
④ 悪性症候群との違いについて
セロトニン症候群は悪性症候群(後述します)と類似の症状を示すことが多く、とりわけ重篤症例やセロトニン作動薬と抗精神病薬との併用例では鑑別が困難なことがありますので、十分な注意が必要です。錯乱、軽躁状態、ミオクローヌス、反射亢進などがセロトニン症候群に特異的な症状とされています。
(2)悪性症候群
悪性症候群は抗精神病薬の代表的な副作用の一つですが、抗精神病薬に限らず向精神薬すべてにおける副作用では死亡率の高い最も重篤なものです。
① 症状と発症時期
特徴的な初期症状は、解熱薬に反応しない持続性の高熱、発汗、頻脈などの自律神経症状、振戦、筋強剛、無動・緘黙などの錐体外路症状、言語障害、流延(唾液の分泌過多)、嚥下障害、意識障害などが見られます。
この時期に早期に発見し、直ぐに治療することが重篤な状態に至らせない重要なポイントです。これらが認められた時は、直ちに手を打たなければその後、肺炎、腎不全、心不全、けいれん、敗血症、肺梗塞などを発症し致命的になることがあります。
発症時期は服薬開始から2週間以内がほとんどですが、2週間以降に発症する遅発型もあり、長期の服用によっても起こる可能性があります。また、原因薬物の用量変更(追加や増加など)や抗パーキンソン病薬の中断により発症する場合もあります。
② 発症要因
*患者側の要因
患者さんの80%以上が発症前に精神、身体状態に何らかの異常を示しており、不穏、興奮、拒食、不眠、脱水、低栄養などの精神状態、身体状態の悪化が特徴的です。
これらが発症準備状態を形成し、薬物側の要因によって悪性症候群が誘発されると考えられています。
*原因薬物の要因
ドパミン受容体遮断作用を有する抗精神病薬は発症頻度が高く、とりわけ遮断作用の強い薬物ほど起こりやすいとされています。ドパミン以外の受容体に作用する抗うつ薬による発症や炭酸リチウムとの併用によって発現率が高くなるとの報告もあります。
③ 治療
発症に際しては迅速な医学的な処置が絶対に必要ですので、直ちに専門医の適切な治療を受けて手遅れにならぬようにすることが重要です。治療としては、全ての向精神薬を中止し、輸液などの身体管理を行い、ダントロレンナトリウム(ダントリウム)を投与します。
*悪性症候群を引き起こす可能性のある、特に抗精神病薬の多剤併用処方などに十分に注意して、これを起こさないことが大前提ですが、もし起きてしまった時は速やかな対処治療が必要になることを認識しておくことが重要です。
(3)アクチベーション症候群(賦活症候群)
若年期の自殺念慮とSSRIとの因果関係で注目される中枢神経刺激症状ですが、抗うつ薬開始後にみられる攻撃性・衝動性の亢進や自傷行為の増加は本症候群の一部である可能性が高いと考えられています。
このような症状は新たに抗うつ薬が処方された患者の4%強にみられたとの報告もあり、SSRI,SNRIに限ったことではなく三環系、四環系抗うつ薬でも発現しうると考えられています。
① 症状と発症時期
主な症状は次の10の症状が挙げられています。不安、焦燥、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、衝動性、アカシジア、軽躁状態、躁状態SSRIを服用した患者が急に攻撃性を増すことで、子供など家族に危害を加えるなどの例が少なからず報告され社会問題化しており、また高齢者では興奮状態になる患者もいる。
発症時期は服薬の初期や用量の変更時(追加や増加)に発現しやすいとされている。
② 処置
本症候群は一過性で、速やかな医療機関の受診と適切な処置(抗うつ薬の中止、減薬など)により改善します。しかしながら、本症候群の症状は原疾患(うつ病)の症状に類似しており、医学的な処置については患者の状態が「アクチベーション症候群による症状」なのか「原疾患(うつ病)の増悪による症状」なのかを適切に鑑別し、見極めることが非常に重要であり、対応処置を間違えると更に患者を苦しめることになります。
医師の鑑別能力(薬に対する知識、経験や患者の病状判断能力と経験など)の有無が非常に重要になってきます。この鑑別能力は前述のセロトニン症候群、悪性症候群の鑑別についても同じことが当てはまります。
(4)妊産婦への悪影響
一般的に薬物はその種類によらず、妊娠中に服用すべきではないといわれます。その理由は、胎児に何らかの形で悪影響を及ぼす可能性があるからです。
抗うつ薬などの向精神薬はその悪影響が大きい薬剤の一つと言っても過言ではありません。SSRIは女性が服用した場合、不妊の可能性があり、妊娠時の母体への薬毒性の影響、妊娠後には流産や早産、胎児の先天異常(心臓奇形など)のリスクを高め、更には出生後に起きる新生児の重大な急性症状などさまざまな悪影響を及ぼす可能性が高いのです。
① 胎児に及ぼす影響の中で重要な問題は催奇形性です。
薬の投与量が多いほど発生率が上がり、危険度が増します。その多くは、唇裂、口蓋裂、心臓の奇形、骨の奇形です。
② 「新生児適合不良」症状の発現
母親が妊娠中に服用していたSSRIは胎内でそのまま胎児に移行します。
流産や早産はそのために起きると考えられますが、無事に出生できたとしても母体内とは環境が一変して、新生児のSSRIの血中濃度は急激に低下します。その出生環境の激変に適応しきれないためにけいれんや急激な呼吸困難を中心とする症状(呼吸窮迫症)や持続性の肺動脈高血圧(新生児遷延性肺高血圧症)などが多く発現することが疫学調査などで確かめられています。
これらの症状は、出生により新生児の体内からSSRIが急速に減少したための離脱症候群と考えられていますが、中毒性の変化である可能性も否定しきれないので「新生児適合不良」と呼ばれています。
③ 精神神経系への発達障害
胎内でSSRI依存状態になった胎児が、出生後に離脱症候群としてけいれんや無呼吸発作、循環虚脱、昏睡など重篤な有害反応を受けた子供は、その後のセロトニン系の正常な発達が阻害され、ひいては精神神経系の発達に障害が残る可能性が懸念されるのです。
④ 減薬、断薬の実行
胎児に影響を及ぼす可能性が高いのは妊娠第12週までと言われ、この時期は患者さん自身が妊娠を知らずに薬を飲み続けている可能性があります。
これまで述べました重大な悪影響を考えると妊娠中はもちろんのこと、妊娠可能な女性はSSRIをはじめ向精神薬を服用すべきではありません。現在すでに服用している場合も、少しずつ減薬していき、最終的には中止するようにすべきと考えます。
(5)錐体外路症状(EPS)
錐体外路症状とは主に抗精神病薬を中心とするドパミン受容体遮断作用を有する薬剤によって引き起こされる障害ですが、SSRIの服用によっても発現することがあります。
脳の黒質線条体のドーパミン受容体が過剰に遮断されることにより、不随意運動を司る神経が通る錐体外路系が正常に働かなくなって起こります。
① 症状
*アキネジア、パーキンソン病様症状
筋緊張が亢進して筋肉が滑らかに動かずに運動が減少することにより、筋強剛、振戦、小刻み歩行、すり足歩行などが出てくる。
*ジストニア
筋緊張が異常となり、強直、捻転が生じ奇妙な姿勢となる。抗精神病薬の投与初期や増量によって早期に見られる。
*アカシジア
手や足に不快感が生じ、特に足の不快感がひどいために歩き回り、じっと座っていられない(正座できない)状態
*遅発性ジスキネジア
抗精神病薬を長期(数か月~数年)に服用した後に急に発現する症状で、絶えず口をモグモグと咀嚼運動のように動かしたり、舌を出したり戻したりを繰り返したりする。
② 対処方法
錐体外路症状が出現したときは、抗パーキンソン病薬を投与するのが一般的です。しかし、抗パーキンソン病薬は使わないに越したことは無い薬であり、医師は最初から使わなくても済むような薬物治療を心がけることが望まれます。尚、抗パーキンソン病薬はその止め方にも注意が必要です。急に一挙に止めてしまいますと色々な断薬症状(禁断症状)が発現しますので、徐々に減薬していく必要があります。
(6)減薬、断薬による離脱症状(禁断症状)
向精神薬を減薬、断薬する際に最も注意するべき問題は、薬の離脱症状(禁断症状)が程度の違いはあっても必ず発現して、患者さんを苦しめることです。
いろいろな症状が出てきますが、その対応が難しい非常に厄介な症状です。新世代の抗うつ薬のSSRI,SNRIにも減薬、断薬時には発現してきます。従来薬(三環系、四環系抗うつ薬)でも何らかの形で症状が起こることはありますが、従来薬は多くの神経伝達物質に関連した部位に影響を及ぼしているため、薬物を中止しても全体にホメオスタシス(恒常性)を保ちながら薬物の影響が無くなっていくので、症状を際立って自覚することは少ない。
しかし、SSRI,SNRIは限られた一部の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン)だけが変化するため、服用を中止するとホメオスタシスが急激に崩れることで症状が派手に出現してきます。
① 症状と発症時期
*離脱症状は次のように多様な症状が発現します。
不安、恐怖、興奮、悪夢、めまい、ふらつき、悪心、かすみ目、不眠、筋けいれん、頭痛、震え、発汗、動悸、耳鳴り、知覚異常、知覚過敏、電気ショック感、むずむず脚、自傷行為、自殺など
*発症時期
この症状は4週間以上の継続投与後に、急に減薬ないし中止すると多くはその後2~3日以内に発現します。これは身体、特に脳内のセロトニン系のそれまでの恒常性が変化することによって起こると推定されています。
② 対応処置
一番の対応(予防)処置は、急に減薬ないし中止しないで患者さんの体調変化に十分注意を払いながら、ゆっくりと徐々に減薬していくことです。
③ 症状の残存期間
これら症状が断薬後、どのくらいの期間続くかについては個人差が大きくまちまちですが、半年後にはおよそ8割の方が回復するといわれています。しかし、中には数年も持続することもあり、永続的に残ってしまう場合が有るといわれています。その症状は
*記憶障害、感情の平板化、頭がうまく働かないといった認知能力に関する事
*無気力、意欲の低下などの抑うつ症状
*イライラする、些細な事に過敏に反応するなどの情緒の不安定化などがあります。
④ 離脱症状をきちんと判別できる医師は少ない
離脱症状について大きな問題点は、医師が離脱症状をきちんと正確に判別できるか、ということです。前述の副作用(セロトニン症候群、アクチベーション症候群)の項目でも述べましたが、医師の鑑別能力の問題です。
薬の減薬時や断薬後に生じる様々な離脱症状は、原疾患(うつ病)の病気の症状と非常によく類似していますので、患者さんに現れている離脱症状を離脱症状と見抜けずに、病気の再発や悪化として診てしまう医師が非常に多いのです。
そうすると、その症状を抑えるために薬を追加で処方したり、さらに強い薬へと移行していくことになってしまうのです。このような医師に治療を受けている場合は、薬漬けになってしまう危険が大きいと言わざるを得ません。
(7)「医療用医薬品の添付文書」について
「医療用医薬品の添付文書」とは、製薬会社が医師や薬剤師などの専門家向けに薬の副作用などを詳しく記載した文書です。
一般的に、病院や調剤薬局から薬とともに渡される薬の説明書の注意事項は、例えば、「食欲がない、口が渇く、眠気、めまい、気持ちが悪い、腹痛、下痢などが現れることがあります。
「眠気や注意力の低下が現れることがありますので車の運転や危険を伴う作業は控えてください。」などという程度の内容です。これでは、薬の副作用が及ぼす重大な悪影響を把握することは出来ません。
「医療用医薬品の添付文書」は、医師や薬剤師などの専門家向けに作られたものですので、重大な副作用などがきちんと記載されているのです。抗うつ薬などの向精神薬は、人間にとって最も重要でデリケートな器官である脳組織(神経細胞やホルモンなど)に直接的に作用し、働きかける薬ですので、その副作用の内容については十分に認識し、使用に際しては最大限の注意を払うべきなのです。
その為にも、自分が飲んでいる薬について、是非、「医療用医薬品の添付文書」をお読みいただき、薬の副作用について調べてみることをお勧めいたします。また、「医療用医薬品の添付文書」ほど詳しい説明、記述ではありませんが、もう少し一般的に解説されている「くすりのしおり」というサイトも有りますので、参考にしてください。
◎「医療用医薬品の添付文書」のサイト
http://info.pmda.go.jp/psearch/html/menu-tenpu-base.html
◎「くすりのしおり」のサイト
http://rad-ar.or.jp/siori/index.html